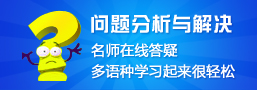日语小说连载:地獄変4
来源: 万语网 | 更新日期:2007-08-21 18:15:49 | 浏览(175)人次
|
十六 それから二三日した夜の事でございます。大殿様は御約束通り、良秀を御召しになつて、檳榔毛の車の焼ける所を、目近く見せて御やりになりました。尤もこれは堀河の御邸であつた事ではございません。俗に雪解《ゆきげ》の御所と云ふ、昔大殿様の妹君がいらしつた洛外の山荘で、御焼きになつたのでございます。 この雪解の御所と申しますのは、久しくどなたも御住ひにはならなかつた所で、広い御庭も荒れ放題荒れ果てて居りましたが、大方この人気のない御容子を拝見した者の当推量でございませう。こゝで御歿《おな》くなりになつた妹君の御身の上にも、兎角の噂が立ちまして、中には又月のない夜毎々々に、今でも怪しい御袴《おんはかま》の緋の色が、地にもつかず御廊下を歩むなどと云ふ取沙汰を致すものもございました。――それも無理ではございません。昼でさへ寂しいこの御所は、一度日が暮れたとなりますと、遣《や》り水《みづ》の音が一際《ひときは》陰に響いて、星明りに飛ぶ五位鷺も、怪形《けぎやう》の物かと思ふ程、気味が悪いのでございますから。 丁度その夜はやはり月のない、まつ暗な晩でございましたが、大殿油《おほとのあぶら》の灯影で眺めますと、縁に近く座を御占めになつた大殿様は、浅黄の直衣《なほし》に濃い紫の浮紋の指貫《さしぬき》を御召しになつて、白地の錦の縁をとつた円座《わらふだ》に、高々とあぐらを組んでいらつしやいました。その前後左右に御側の者どもが五六人、恭しく居並んで居りましたのは、別に取り立てて申し上げるまでもございますまい。が、中に一人、眼だつて事ありげに見えたのは、先年|陸奥《みちのく》の戦ひに餓ゑて人の肉を食つて以来、鹿の生角《いきづの》さへ裂くやうになつたと云ふ強力《がうりき》の侍が、下に腹巻を着こんだ容子で、太刀を鴎尻《かもめじり》に佩《は》き反《そ》らせながら、御縁の下に厳《いかめ》しくつくばつてゐた事でございます。――それが皆、夜風に靡《なび》く灯の光で、或は明るく或は暗く、殆ど夢現《ゆめうつゝ》を分たない気色で、何故かもの凄く見え渡つて居りました。 その上に又、御庭に引き据ゑた檳榔毛の車が、高い車蓋《やかた》にのつしりと暗《やみ》を抑へて、牛はつけず黒い轅《ながえ》を斜に榻《しぢ》へかけながら、金物《かなもの》の黄金《きん》を星のやうに、ちらちら光らせてゐるのを眺めますと、春とは云ふものゝ何となく肌寒い気が致します。尤もその車の内は、浮線綾の縁《ふち》をとつた青い簾が、重く封じこめて居りますから、※[#「車+非」、第4水準2-89-66]《はこ》には何がはいつてゐるか判りません。さうしてそのまはりには仕丁たちが、手ん手に燃えさかる松明《まつ》を執つて、煙が御縁の方へ靡くのを気にしながら、仔細《しさい》らしく控へて居ります。 当の良秀は稍《やゝ》離れて、丁度御縁の真向に、跪《ひざまづ》いて居りましたが、これは何時もの香染めらしい狩衣に萎《な》えた揉烏帽子を頂いて、星空の重みに圧されたかと思ふ位、何時もよりは猶小さく、見すぼらしげに見えました。その後に又一人、同じやうな烏帽子狩衣の蹲《うづくま》つたのは、多分召し連れた弟子の一人ででもございませうか。それが丁度二人とも、遠いうす暗がりの中に蹲つて居りますので、私のゐた御縁の下からは、狩衣の色さへ定かにはわかりません。 十七 時刻は彼是真夜中にも近かつたでございませう。林泉をつゝんだ暗がひつそりと声を呑んで、一同のする息を窺つてゐると思ふ中には、唯かすかな夜風の渡る音がして、松明の煙がその度に煤臭い匂を送つて参ります。大殿様は暫く黙つて、この不思議な景色をぢつと眺めていらつしやいましたが、やがて膝を御進めになりますと、 「良秀、」と、鋭く御呼びかけになりました。 良秀は何やら御返事を致したやうでございますが、私の耳には唯、唸るやうな声しか聞えて参りません。 「良秀。今宵はその方の望み通り、車に火をかけて見せて遣はさう。」 大殿様はかう仰有つて、御側の者たちの方を流《なが》し眄《め》に御覧になりました。その時何か大殿様と御側の誰彼との間には、意味ありげな微笑が交されたやうにも見うけましたが、これは或は私の気のせゐかも分りません。すると良秀は畏《おそ》る畏《おそ》る頭を挙げて御縁の上を仰いだらしうございますが、やはり何も申し上げずに控へて居ります。 「よう見い。それは予が日頃乗る車ぢや。その方も覚えがあらう。――予はその車にこれから火をかけて、目のあたりに炎熱地獄を現ぜさせる心算《つもり》ぢやが。」 大殿様は又言を御止めになつて、御側の者たちに※[#「目+旬」、第3水準1-88-80]《めくば》せをなさいました。それから急に苦々しい御調子で、「その内には罪人の女房が一人、縛《いまし》めた儘、乗せてある。されば車に火をかけたら、必定その女めは肉を焼き骨を焦して、四苦八苦の最期を遂げるであらう。その方が屏風を仕上げるには、又とないよい手本ぢや。雪のやうな肌が燃え爛《たゞ》れるのを見のがすな。黒髪が火の粉になつて、舞ひ上るさまもよう見て置け。」 大殿様は三度口を御噤《おつぐ》みになりましたが、何を御思ひになつたのか、今度は唯肩を揺つて、声も立てずに御笑ひなさりながら、 「末代までもない観物ぢや。予もここで見物しよう。それ/\、簾《みす》を揚げて、良秀に中の女を見せて遣さぬか。」 仰《おほせ》を聞くと仕丁の一人は、片手に松明《まつ》の火を高くかざしながら、つか/\と車に近づくと、矢庭に片手をさし伸ばして、簾をさらりと揚げて見せました。けたゝましく音を立てて燃える松明の光は、一しきり赤くゆらぎながら、忽ち狭い※[#「車+非」、第4水準2-89-66]《はこ》の中を鮮かに照し出しましたが、※[#「車+因」、第4水準2-89-62]《とこ》の上に惨《むごた》らしく、鎖にかけられた女房は――あゝ、誰か見違へを致しませう。きらびやかな繍《ぬひ》のある桜の唐衣《からぎぬ》にすべらかし黒髪が艶やかに垂れて、うちかたむいた黄金の釵子《さいし》も美しく輝いて見えましたが、身なりこそ違へ、小造りな体つきは、色の白い頸《うなじ》のあたりは、さうしてあの寂しい位つゝましやかな横顔は、良秀の娘に相違ございません。私は危く叫び声を立てようと致しました。 その時でございます。私と向ひあつてゐた侍は慌《あわたゞ》しく身を起して、柄頭《つかがしら》を片手に抑へながら、屹《きつ》と良秀の方を睨みました。それに驚いて眺めますと、あの男はこの景色に、半ば正気を失つたのでございませう。今まで下に蹲《うづくま》つてゐたのが、急に飛び立つたと思ひますと、両手を前へ伸した儘、車の方へ思はず知らず走りかゝらうと致しました。唯生憎前にも申しました通り、遠い影の中に居りますので、顔貌《かほかたち》ははつきりと分りません。しかしさう思つたのはほんの一瞬間で、色を失つた良秀の顔は、いや、まるで何か目に見えない力が、宙へ吊り上げたやうな良秀の姿は、忽ちうす暗がりを切り抜いてあり/\と眼前へ浮び上りました。娘を乗せた檳榔毛の車が、この時、「火をかけい」と云ふ大殿様の御言と共に、仕丁たちが投げる松明の火を浴びて炎々と燃え上つたのでございます。 十八 火は見る/\中に、車蓋《やかた》をつゝみました。庇《ひさし》についた紫の流蘇《ふさ》が、煽られたやうにさつと靡くと、その下から濛々と夜目にも白い煙が渦を巻いて、或は簾《すだれ》、或は袖、或は棟《むね》の金物《かなもの》が、一時に砕けて飛んだかと思ふ程、火の粉が雨のやうに舞ひ上る――その凄じさと云つたらございません。いや、それよりもめらめらと舌を吐いて袖格子《そでがうし》に搦《から》みながら、半空《なかぞら》までも立ち昇る烈々とした炎の色は、まるで日輪が地に落ちて、天火《てんくわ》が迸《ほとばし》つたやうだとでも申しませうか。前に危く叫ばうとした私も、今は全く魂《たましひ》を消して、唯茫然と口を開きながら、この恐ろしい光景を見守るより外はございませんでした。しかし親の良秀は―― 良秀のその時の顔つきは、今でも私は忘れません。思はず知らず車の方へ駆け寄らうとしたあの男は、火が燃え上ると同時に、足を止めて、やはり手をさし伸した儘、食ひ入るばかりの眼つきをして、車をつゝむ焔煙を吸ひつけられたやうに眺めて居りましたが、満身に浴びた火の光で、皺だらけな醜い顔は、髭の先までもよく見えます。が、その大きく見開いた眼の中と云ひ、引き歪めた唇のあたりと云ひ、或は又絶えず引き攣《つ》つてゐる頬の肉の震《ふる》へと云ひ、良秀の心に交々《こも/″\》往来する恐れと悲しみと驚きとは、歴々と顔に描かれました。首を刎《は》ねられる前の盗人でも、乃至は十王の庁へ引き出された、十逆五悪の罪人でも、あゝまで苦しさうな顔を致しますまい。これには流石にあの強力《がうりき》の侍でさへ、思はず色を変へて、畏る/\大殿様の御顔を仰ぎました。 が、大殿様は緊《かた》く唇を御噛みになりながら、時々気味悪く御笑ひになつて、眼も放さずぢつと車の方を御見つめになつていらつしやいます。さうしてその車の中には――あゝ、私はその時、その車にどんな娘の姿を眺めたか、それを詳しく申し上げる勇気は、到底あらうとも思はれません。あの煙に咽《むせ》んで仰向《あふむ》けた顔の白さ、焔を掃《はら》つてふり乱れた髪の長さ、それから又見る間に火と変つて行く、桜の唐衣《からぎぬ》の美しさ、――何と云ふ惨《むご》たらしい景色でございましたらう。殊に夜風が一下《ひとおろ》しして、煙が向うへ靡いた時、赤い上に金粉を撒《ま》いたやうな、焔の中から浮き上つて、髪を口に噛みながら、縛《いましめ》の鎖も切れるばかり身悶えをした有様は、地獄の業苦を目のあたりへ写し出したかと疑はれて、私始め強力の侍までおのづと身の毛がよだちました。 するとその夜風が又一渡り、御庭の木々の梢にさつと通ふ――と誰でも、思ひましたらう。さう云ふ音が暗い空を、どことも知らず走つたと思ふと、忽ち何か黒いものが、地にもつかず宙にも飛ばず、鞠《まり》のやうに躍りながら、御所の屋根から火の燃えさかる車の中へ、一文字にとびこみました。さうして朱塗のやうな袖格子が、ばら/\と焼け落ちる中に、のけ反《ぞ》つた娘の肩を抱いて、帛《きぬ》を裂くやうな鋭い声を、何とも云へず苦しさうに、長く煙の外へ飛ばせました。続いて又、二声三声――私たちは我知らず、あつと同音に叫びました。壁代《かべしろ》のやうな焔を後にして、娘の肩に縋《すが》つてゐるのは、堀河の御邸に繋いであつた、あの良秀と諢名《あだな》のある、猿だつたのでございますから。その猿が何処をどうしてこの御所まで、忍んで来たか、それは勿論誰にもわかりません。が、日頃可愛がつてくれた娘なればこそ、猿も一しよに火の中へはひつたのでございませう。 十九 が、猿の姿が見えたのは、ほんの一瞬間でございました。金梨子地《きんなしぢ》のやうな火の粉が一しきり、ぱつと空へ上つたかと思ふ中に、猿は元より娘の姿も、黒煙の底に隠されて、御庭のまん中には唯、一輛の火の車が凄《すさま》じい音を立てながら、燃《も》え沸《たぎ》つてゐるばかりでございます。いや、火の車と云ふよりも、或は火の柱と云つた方が、あの星空を衝いて煮え返る、恐ろしい火焔の有様にはふさはしいかも知れません。 その火の柱を前にして、凝り固まつたやうに立つてゐる良秀は、――何と云ふ不思議な事でございませう。あのさつきまで地獄の責苦《せめく》に悩んでゐたやうな良秀は、今は云ひやうのない輝きを、さながら恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮べながら、大殿様の御前も忘れたのか、両腕をしつかり胸に組んで、佇《たゝず》んでゐるではございませんか。それがどうもあの男の眼の中には、娘の悶え死ぬ有様が映つてゐないやうなのでございます。唯美しい火焔の色と、その中に苦しむ女人の姿とが、限りなく心を悦ばせる――さう云ふ景色に見えました。 しかも不思議なのは、何もあの男が一人娘の断末魔を嬉しさうに眺めてゐた、そればかりではございません。その時の良秀には、何故か人間とは思はれない、夢に見る獅子王の怒りに似た、怪しげな厳《おごそか》さがございました。でございますから不意の火の手に驚いて、啼き騒ぎながら飛びまはる数の知れない夜鳥でさへ、気のせゐか良秀の揉烏帽子のまはりへは、近づかなかつたやうでございます。恐らくは無心の鳥の眼にも、あの男の頭の上に、円光の如く懸つてゐる、不可思議な威厳が見えたのでございませう。 鳥でさへさうでございます。まして私たちは仕丁までも、皆息をひそめながら、身の内も震へるばかり、異様な随喜の心に充ち満ちて、まるで開眼の仏でも見るやうに、眼も離さず、良秀を見つめました。空一面に鳴り渡る車の火と、それに魂を奪はれて、立ちすくんでゐる良秀と――何と云ふ荘厳、何と云ふ歓喜でございませう。が、その中でたつた一人、[#「たつた一人、」は底本では「たつた、」]御縁の上の大殿様だけは、まるで別人かと思はれる程、御顔の色も青ざめて、口元に泡を御ためになりながら、紫の指貫《さしぬき》の膝を両手にしつかり御つかみになつて、丁度喉の渇いた獣のやうに喘《あへ》ぎつゞけていらつしやいました。…… 二十 その夜雪解の御所で、大殿様が車を御焼きになつた事は、誰の口からともなく世上へ洩れましたが、それに就いては随分いろ/\な批判を致すものも居つたやうでございます。先《まづ》第一に何故《なぜ》大殿様が良秀の娘を御焼き殺しなすつたか、――これは、かなはぬ恋の恨みからなすつたのだと云ふ噂が、一番多うございました。が、大殿様の思召しは、全く車を焼き人を殺してまでも、屏風の画を描かうとする絵師根性の曲《よこしま》なのを懲らす御心算《おつもり》だつたのに相違ございません。現に私は、大殿様が御口づからさう仰有《おつしや》るのを伺つた事さへございます。 それからあの良秀が、目前で娘を焼き殺されながら、それでも屏風の画を描きたいと云ふその木石のやうな心もちが、やはり何かとあげつらはれたやうでございます。中にはあの男を罵《のゝし》つて、画の為には親子の情愛も忘れてしまふ、人面獣心の曲者《くせもの》だなどと申すものもございました。あの横川《よがは》の僧都様などは、かう云ふ考へに味方をなすつた御一人で、「如何に一芸一能に秀でやうとも、人として五常を弁《わきま》へねば、地獄に堕ちる外はない」などと、よく仰有つたものでございます。 所がその後一月ばかり経《た》つて、愈々地獄変の屏風が出来上りますと良秀は早速それを御邸へ持つて出て、恭しく大殿様の御覧に供へました。丁度その時は僧都様も御居合はせになりましたが、屏風の画を一目御覧になりますと、流石にあの一帖の天地に吹き荒《すさ》んでゐる火の嵐の恐しさに御驚きなすつたのでございませう。それまでは苦い顔をなさりながら、良秀の方をじろ/\睨めつけていらしつたのが、思はず知らず膝を打つて、「出かし居つた」と仰有いました。この言を御聞きになつて、大殿様が苦笑なすつた時の御容子も、未だに私は忘れません。 それ以来あの男を悪く云ふものは、少くとも御邸の中だけでは、殆ど一人もゐなくなりました。誰でもあの屏風を見るものは、如何に日頃良秀を憎く思つてゐるにせよ、不思議に厳《おごそ》かな心もちに打たれて、炎熱地獄の大苦艱《だいくげん》を如実に感じるからでもございませうか。 しかしさうなつた時分には、良秀はもうこの世に無い人の数にはいつて居りました。それも屏風の出来上つた次の夜に、自分の部屋の梁《はり》へ縄をかけて、縊《くび》れ死んだのでございます。一人娘を先立てたあの男は、恐らく安閑として生きながらへるのに堪へなかつたのでございませう。屍骸は今でもあの男の家の跡に埋まつて居ります。尤も小さな標《しるし》の石は、その後何十年かの雨風《あめかぜ》に曝《さら》されて、とうの昔誰の墓とも知れないやうに、苔蒸《こけむ》してゐるにちがひございません。 [#地から2字上げ]――大正七年四月―― 底本:「芥川龍之介全集 第一巻」岩波書店 1995(平成7)年11月8日発行 底本の親本:「鼻」春陽堂 1918(大正7)年7月8日発行 ※底本には「堀川」と「堀河」が共に現れる。「堀河」は「堀川」と思われるが、表記の揺れは底本のママとした。 入力:earthian 校正:j.utiyama 1998年12月2日公開 2004年3月8日修正 |
| 课程名称 | 有效期 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
| 240天 | 80节 | 370.0元 |
|
|||
| 240天 | 75节 | 480.0元 |
|
|||
|
155节 | 590.0元 | ||||
| 360天 | 243节 | 590.0元 |
|
|||
|
398节 | 840.0元 | ||||
| 240天 | 96节 | 498.0元 |
|
|||
| 240天 | 96节 | 498.0元 |
|
|||
|
192节 | 898.0元 | ||||
| 60天 | 19节 | 198.0元 |
|
|||
| 240天 | 60节 | 500.0元 |
|
|||
| 120天 | 37节 | 398.0元 |
|
|||
| 150天 | 15节 | 258.0元 |
|
|||
| 150天 | 18节 | 358.0元 |
|
|||
|
52节 | 498.0元 |
你可能感兴趣的文章
- 日本語の常識1:切るのになぜ“刺す"か(在线日语学习网) 2018-11-09
- (中日对照)日本的便当(日语视频学习网) 2018-11-09
- 原创日语古典俳句(日语培训网) 2018-11-09
- 日本前首相鸠山由纪夫成为国内大学名誉教授(日语学习网) 2018-11-06
- 日本中小学“光盘行动”引争议(日语培训网) 2018-11-06
 万语空间
万语空间